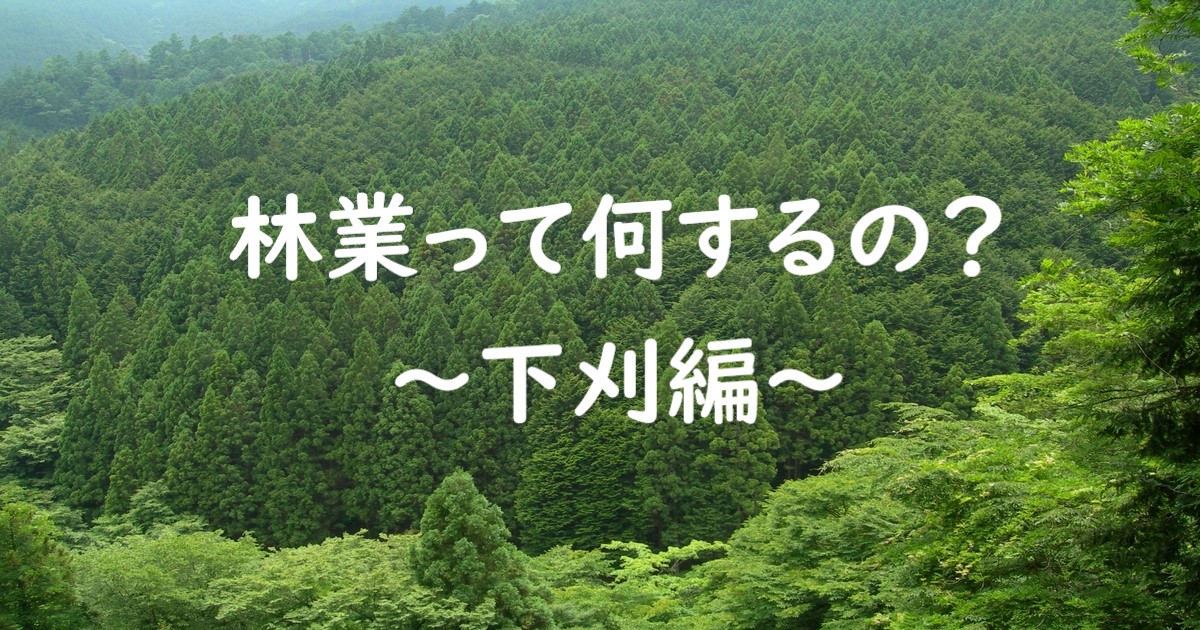こんにちは、イチです。
6月になって最初のブログ更新は林業の「下刈」です。
6月は林業(造林)で下刈がメインになるタイミングなんですよね
だいたい9月頃まで、つまり4か月くらいは「下刈」ばかりをしています。
以下で詳述していきます!
下刈って?
林業記事で決まって書いている、林業のサイクルをもう一度確認しておきます。
植林(植え付け、植栽)
→下刈、除伐、間伐(育てる)
→皆伐(伐採)
→地拵え(植林準備)
→植林…
上のサイクルでは2番目、つまり植林の次の作業であることが分かります。
こちらも林業に従事してから知った作業ですね…
木を育てるのは植えて終わりではなく大変な手間がかかる、といえます。
でも、初めて知ったときは何だか愛おしく感じましたね。
大切に育てるぞーみたいな笑
目的
簡潔に表現すれば、「木の生育の邪魔になる雑草を刈ること」です。
山にヒノキやスギといった木を植えますが、木の成長は雑草より遅いんですよ。
だから雑草のせいで木の成長が阻害されてしまうんです
その事態を避けるために行うのが「下刈」というわけです。
まずは写真をお見せしようと思います。
こちらが下刈前。

そして、以下の写真が下刈後を同じ角度で撮ったものです。

地面がすっきりしている様子が分かると思います!
上の写真でも左あたりは下刈済なので、少しその切れ目がわかるかも…?
そして植えてから毎年、5年間は下刈を行います。
最近いろいろと変わったため「5年間のうちに3回」という感じになったはずですが…(例外アリ)
そして下刈後の木々は、おおよそどんな雑草にも負けない大きさになってくれます!
また私の職場は暑さ対策のために、下刈をする時間は朝6時から14時までという勤務時間になっています。
普段より2時間早く始まり、3時間早く終わります。
普段の労働時間は7時間なんですが、6時間になってますね
なんか計算が合わないんですが、早朝出勤を加味してのことだと思います。
私は朝起きるのが苦でないので助かってますが、苦手な人はツラいかも…?
時期
基本的に夏に行うのですが、その理由は2つあって、
①雑草木の成長が著しく、負担を最も主林木(ヒノキ等)にかけてしまう時期だから
②雑草木のエネルギーが成長に向けて使い果たされていて、ここで刈ってしまうことで来春に向けてのエネルギー蓄積を阻害できるから
というものになります。
あとは当然ですが、かなり暑いです!
それに加え山特有のしんどさがあります。
具体的には斜面やハチ、トゲのある植物などになるでしょうか
造林の作業の中でも一番キツいという人が多いです。
道具
以下で紹介していきます。
個人差もありますので参考程度にとらえてください
○ヘルメット

飛来物や落下物から頭部を守るだけでなく、フェイスガード(網状の部分)やイヤーマフ(防音装備)がついているのも重宝しています。
やや重たいのがネックですが…
使用して3年目になったヘルメット。
そろそろ交換時期ですね
○ゴーグル

フェイスガードをしていますが、こちらも併用していました。
目に飛んでくると怖いですからね…
念のため、という感じです。
○耳栓
イヤーマフを使用している場合は不要かと思います。
刈払機(エンジン式)の音がかなり大きいので、それを防ぐものです。
音も振動障害(レイノー現象)の原因の一つらしいので…
○刈払機

田んぼのあぜ道や自宅の庭などもこれで刈ってる人が多いですよね。
山林作業用のモデルなので、やや排気量は高め。
私が使っているものはハンドルがU字になっているものですが、他にも色々種類があります。
○笹刈刃
使用している刃はこれです。

そろそろきちんと整えないとダメなんですが、自戒の意味も込めてアップ笑
チップソーと呼ばれる刃を使う事業体もあるようです。
刃についてはまた記事を上げても良いかな? と思っています。
○防振手袋
刈払機からの振動を減少させる手袋です。

必須です!
紹介してきたどの道具もそうですが、けっこう値段によって性能に差があるなと感じています。
防振手袋を仕事で使うのであれば1500円前後のもの、もしくはそれより値段の高いものが良いのではないかな、と思います。
○地下足袋
いろんなものがありますが、私はこれ。

テープ部分にゴミがついてすぐ外れちゃうかな?
と心配していたんですが、問題なしでした。
○下刈セット(腰袋に燃料ボトル、ヤスリ、ポイズンリムーバー、ハサミ、アサリ割り器、プラグ回し、ハチジェット)
①腰袋

私が使用しているのは「電工袋」になります。
まぁ必要な道具類がすべて入れば良いかな? という感じ
ただ腰袋はある程度の「深さ」があった方が良いです。
何かにひっかけたり、滑り落ちたりすると中身が出てしまうので。
②燃料ボトル

シールが剝がれてますが、「エマーソン」の燃料ボトル(1リットル)です。
中には燃料である混合油が入っています。
毎日2本、満タンにしたものを持って山に入っています。
③ヤスリ、ポイズンリムーバー、ハサミ、アサリ割り器、プラグ回し

・ヤスリ
笹刈刃を研ぐものです。
最近は8ミリの太さのものを使用していますね。
・ポイズンリムーバー
ハチに刺された際に、毒を吸い出す際に使用します。
肉があまりないところ、例えば手の甲とかだと絞り出せてるの? って感じもありますが、お守りみたいなものです。
なんだかんだ虫に刺された場合は必ず使用しています。
・ハサミ
木に絡んだツタを切るものです。
このツタが曲者で、木を締め上げて変形させてしまうんです。
私が撮影したものだとこんな感じ。

木材の価値を著しく低下させるので、必ず細いうちに切っておく必要があります。
・アサリ割り器
「刃分け」をする際に使用します。
下刈はそこまで強く刃分けをしなくても良いですが…
この説明までし始めると長くなってしまうので、今回はこのあたりで。
・プラグ回し
機械に刃をセットする際に使用します。
朝イチでつければまず問題ないんですが、まれに途中で必要になることがあるので常備。
・ハチジェット

ハチを撃退するための道具です…が、お守りみたいなものです。
ハチに襲われるときは巣に足を突っ込んだ時や刈り払ってしまったときなんです。
だからハチはすでにブチ切れ状態。
少々薬がかかろうが立ち向かってくるんですよね…
それでも素早く対応できれば身を守れるので、一応持ち運んでいます
方法
植林(植え付け、植栽)の際に気をつけていれば、苗が等高線上に並んでいます。
たとえ苗が小さく、雑草の成長に負けていようとも、等高線上にあれば存在を推測できます
そのために、苗を等高線上に植えるわけですね。
上下に動く必要がないのも、身体的な負担を軽減するポイント。
あとは植林のときと同じように、等高線上に刈り進めます。
そして気持ち、機械の左右の振りをコンパクトになるようにしています。
大振りすると体の負担が多くなりすぎるからです。
斜面が急であれば足腰の負担を考えて上の方まで手を伸ばすことがありますが…
色々なやり方としてがありますが、私の班ではまず一人が境界部分を刈っていきます。
最も下の部分を刈りながら歩くので、この人はやや上下運動をすることになります。
2人目以降は等高線上の最も低いところを刈り、低いところがあれば引き返しつつ、高さをそろえていきます。
端っこまで行けばまた一段上がって刈り進めます。
数人で入っても同じようなかたちです。
とにかく高さが同じようになるように、レベルを上げていくのがポイントです。
こうやって一番上まで刈りきれば下刈は終了となります。
だいたい1人が2反(50mプールくらい)を刈れば1日の作業量としては十分と言われていますね
まとめ
今回は下刈についてまとめました。
作業中はめちゃくちゃ暑いですが、「きれいになった!」という達成感が非常に大きいです
ただやはり熱中症になる人が多い作業ではあります。
サマータイムをしていても暑いときはめちゃくちゃ暑いですからね…。
最近は支給された空調服を着るようになり、熱中症になる人が減りました
空調服はハチ刺されも防ぐことができるようにも感じていて、そういう意味でもありがたい。
今後も休憩や水分補給に気を付けつつ、安全に気をつけて作業していきます!